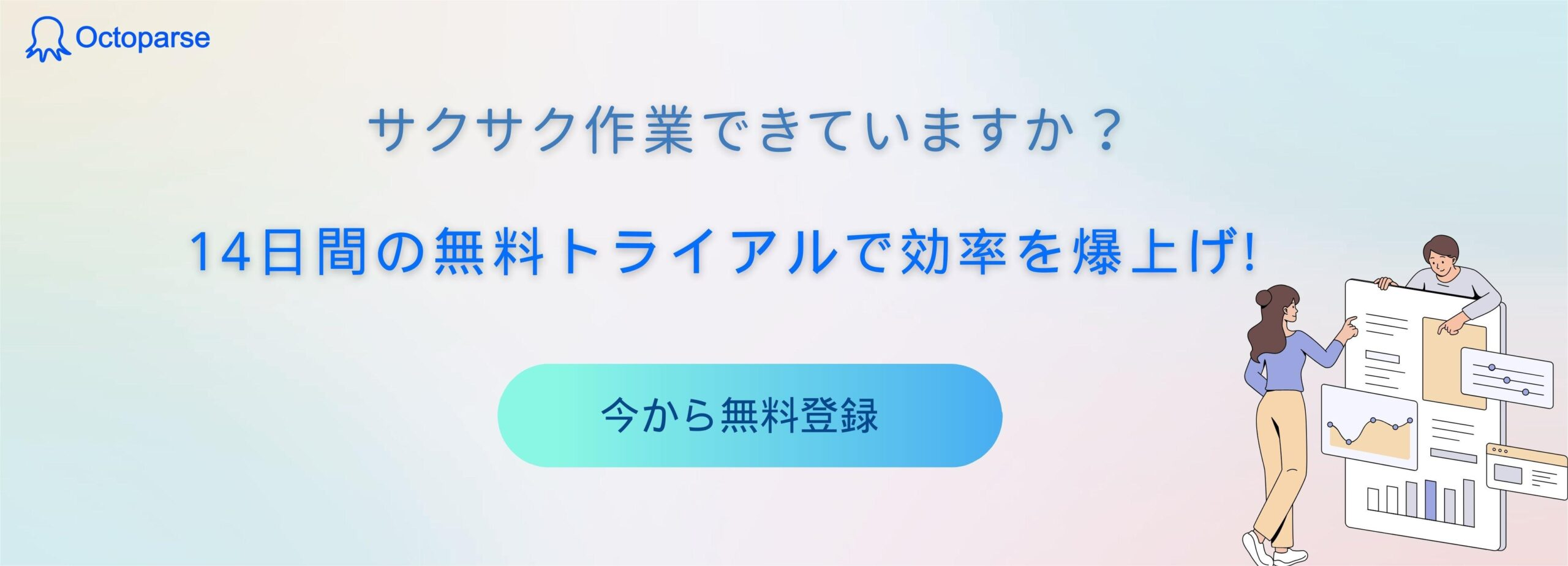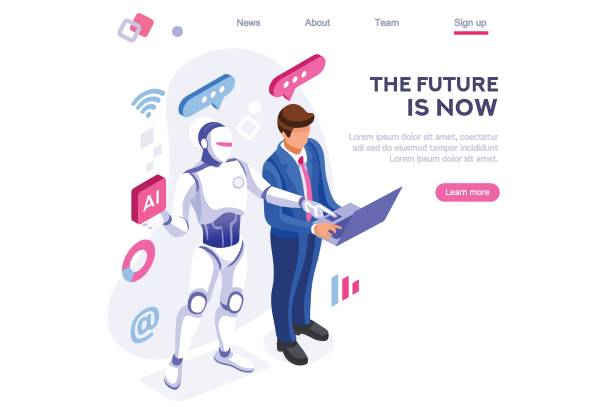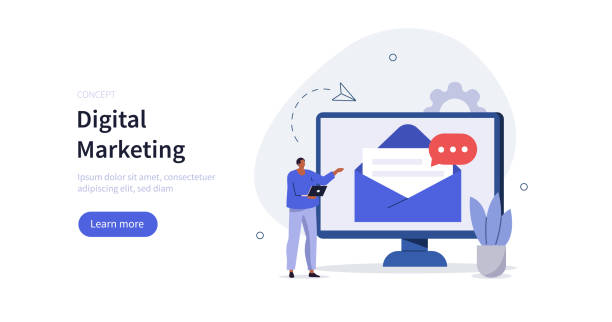デジタルツールの普及に伴い、ビジネスシーンではデータ活用の重要性が高まっています。その中で、特定の部門や業務分野に特化したデータベースとして注目されているのが「データマート」です。
しかし「データマート」という言葉を耳にしたことがあっても「具体的にどういったサービスなのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、データマートの基本から、データマートのメリット・デメリット、おすすめの利用シーンまで、幅広く解説します。データを効率的に活用し、ビジネスの成長を加速させるための知識を身につけましょう。
データマートとは
データマートとは、直訳すると「データの小売店」という意味を持ち、特定の部門や業務分野に関連するデータのみを集約したデータベースのことです。消費者のニーズに応じて様々なデータを収集し、使いやすい形で提供するために用いられます。
企業内に保管されている膨大なデータの中から、目的に合った必要なデータだけを細かく切り分けて格納されるため、データ量は比較的小規模であることが特徴です。例えば、データマートが扱うデータは、特定の部門や業務分野に限定されており、ユーザーのニーズを満たすために処理や加工が施されたデータが格納されています。
このように、必要なデータの抽出が済んでいる状態であるため、ユーザーにとって非常に利用しやすく、特定の業務との相性が良いといえるでしょう。
データウェアハウスとの違い
データウェアハウス(DWH)は、企業内の複数部署や業務分野にわたるデータを一元管理するための統合データベースを指します。DWHでは、事前に必要なデータ項目を整理し、そこにデータを集めていくことが特徴です。
データマートとDWHは似た特徴を持ちますが、格納されるデータの範囲・量と目的・用途に違いがあります。データマートはユーザーに使いやすい形でデータを提供することを目的に作られますが、一方、DWHは一元的にデータを管理し、扱いやすくすることを目的に作られるといった違いがあります。
データレイクとの違い
データレイクは「データの湖」とも訳され、データ形式に関わらずあらゆるデータを一元化できるデータの保存場所のことです。データレイクは、構造化データだけでなく非構造化データも格納できる特徴があり、保管データには一切処理を加えないため、ビッグデータを本来あるべき姿のまま扱うことができます。
データマートが提供するデータは利用目的が明確なのに対し、データレイクに蓄積されるデータは利用目的が決まっていません。その結果、データレイクには未処理のデータが格納され、情報が重複していたり、意味のない情報が存在していたりする場合があります。そのため、必要なタイミングで有効活用できるよう導入する企業が増えています。
データマートのタイプ
データマートは、データの取り込み元によって大きく3つのタイプに分類されます。
- 従属型データマート
- 独立型データマート
- ハイブリッド型データマート
データマートを導入する際は、それぞれの特徴を理解し、予算や規模に合ったものを選択することが重要です。ここでは、各タイプの特徴を見ていきましょう。
従属型データマート
従属型データマートとは、データウェアハウスが既に構築されており、そのデータウェアハウスに従属する形で存在するデータマートのことです。このタイプは、統括的なデータを横断して取り扱うことができる大規模なデータウェアハウスに基づいたトップダウンアプローチを採用しています。
従属型データマートのメリットは、データウェアハウスに集約されたデータから、特定部門が必要とするデータだけを迅速かつ効率的に引き出して利用できることが挙げられます。データウェアハウスに格納されているデータは、ETL処理を経てクレンジングされたデータのみであるため、データの品質が高く、信頼性が高いことが特徴です。
独立型データマート
独立型データマートは、中央のデータウェアハウスに依存せず、スタンドアロンで存在するデータマートです。このタイプでは、各部門が独自の情報源に直接アクセスし、データ収集とETL処理を独立して行います。
独立型データマートのメリットは、大規模なデータウェアハウスを構築することなく、特定のチームやプロジェクトでスモールスタートを切ることができる点にあります。また、将来的にはこれらの独立型データマートからボトムアップ方式で全社を横断するデータウェアハウスを構築することも可能です。
ハイブリッド型データマート
ハイブリッド型データマートは、従属型と独立型の特性を併せ持つタイプです。大部分のデータは中央のデータウェアハウスから取得し、ETL処理済みのデータを効率的に活用しますが、特定部門のデータに関しては独自の情報源から収集し、部門内でETL処理を行う必要があります。
このように、ハイブリット型データマートは、新しい組織や新事業を迅速にサポートできますが、一方で運用管理には注意が必要です。
データマートのメリット
データマートを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。企業はこれらのメリットを活かすことで、データをより効果的に活用し、ビジネスの意思決定を迅速かつ正確に行うことが可能です。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。
導入コストが安価
データマートは、データウェアハウスやデータレイクと比較して、導入コストが比較的安価です。理由としては、データマートが特定の部門や業務に特化しており、必要とするデータの範囲が限定されているため小規模で済むためです。
これにより、初期投資を抑えつつ、必要なデータ分析機能を迅速に提供できます。
短時間で実装できる
データマートは、比較的小規模であるため、短期間で実装できます。特に独立型データマートの場合、1週間程度で構築が可能な場合もあり、迅速にデータ分析の環境を整備することが可能です。
これにより、ビジネスの変化に柔軟に対応し、新たな分析ニーズにもスピーディーに対応できます。
データが扱いやすい
データマートは、特定の業務や部門に特化したデータのみを格納しているため、データの扱いやすさが大きなメリットです。データは事前に加工・整理されているため、分析担当者は必要なデータに素早くアクセスし、分析作業に集中することができます。
また、データマート内のデータは、その業務や部門にとって最も関連性が高い情報のみを含んでいるため、分析の精度も向上します。
データマートのデメリット
データマートの導入は多くのメリットを提供しますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。これらの点を理解し、対策を講じることで、データマートの効果を最大限に引き出すことが可能です。
ランニングコストが掛かる
データマートの導入コストは比較的低いものの、運用を続ける上でランニングコストがかかることがデメリットとして挙げられます。データマートは特定の部門や業務に特化しているため、そのデータを最新の状態に保つためには定期的な更新が必要です。
また、データの品質を維持するための管理や、システムのメンテナンスにもコストが発生します。
複雑な分析や大規模なデータの扱いには向かない
データマートは特定の業務や部門に特化したデータを扱うため、複雑な分析や大規模なデータセットを扱う場合には不向きです。企業全体を横断するような分析や、異なるデータソースを組み合わせた分析を行う場合には、データウェアハウスやデータレイクの方が適しています。
データマートを利用する際には、その限界を理解し、必要に応じて他のデータ管理システムと組み合わせて使用することが重要です。
管理が煩雑になる可能性がある
複数のデータマートを導入する場合、それぞれのデータマートを効率的に管理する必要があります。データマートが増えると、データの整合性を保つための管理作業が複雑になり、管理コストが増大する可能性があります。
また、データマート間でデータを共有する際に、データの重複や矛盾が生じるリスクも考慮する必要があります。
データマートの利用をおすすめするシーン
データマートの利用が特に有効とされるシーンには、以下のような状況があります。これらのシーンでは、データマートの特性を活かして、データ管理と分析の効率を大幅に向上させることが可能です。
社内データの検索に時間が掛かっている場合
企業内に膨大なデータが存在し、必要な情報を見つけ出すのに時間がかかっている場合、データマートの導入が有効です。データマートを利用することで、特定の部門や業務に必要なデータのみを選別し、整理することができます。
これにより、データの検索時間を大幅に短縮し、業勀の効率化を図ることが可能になります。
各現場でデータを活用したい場合
各部門や現場でデータを活用し、より迅速な意思決定を行いたい場合にも、データマートが役立ちます。データマートには、部門や現場で直接関連するデータだけが格納されるため、容易に分析やレポート作成が可能です。
これにより、各現場でのデータ活用が促進され、データ駆動型の意思決定をサポートします。
データ駆動型の意思決定を推進したい場合
企業がデータ駆動型の意思決定をより積極的に推進したい場合、データマートは重要な役割を果たします。データマートによって整理されたデータは、分析に必要な情報を迅速に提供します。
これにより、意思決定プロセスが加速され、ビジネスの機会を逃さずに対応することが可能です。
まとめ
データマートは、特定の部門や業務向けに特化したデータを集約するシステムで、データの分析やレポート作成を効率化します。導入と運用のしやすさが魅力ですが、複雑な分析や大規模なデータセットには向きません。
社内データの迅速な検索、現場でのデータ活用強化、データ駆動型の意思決定推進など、特定のニーズに応える際に特に有効です。適切に導入・活用することで、ビジネスの意思決定を加速し、成長を促進する強力なツールとして活用を期待できるでしょう。