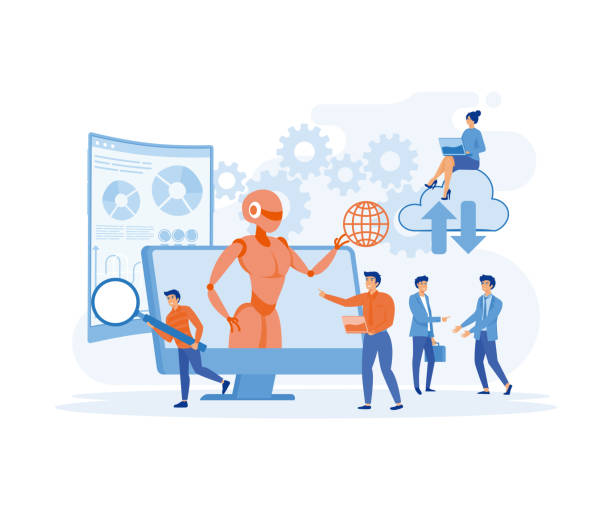はじめに
「AIで仕事は奪われるのか」「会社にAIが導入されたら、次は人員削減が始まるのではないか」──こうした不安を感じたことはありませんか。
近年、AIの発達により「AIに仕事を奪われる」「AIでなくなる仕事が増える」といった話題が、日本でも急速に注目を集めています。AIがもたらす仕事や職業の変化は、もはや遠い未来の話ではなく、すでに現実の課題となりつつあります。
実際、海外でも「AIは本当に仕事を奪うのか?」という議論は活発に行われています。
海外掲示板 Reddit では、事務職やデスクワークなど定型作業の多い仕事からAIの影響を受けやすいという意見が多く見られました。一方で、仕事がなくなる原因はAIそのものではなく、企業がAIを使ってコスト削減を進める判断にある、という冷静な指摘もあります。
※海外掲示板 Reddit 上の複数の議論を参考にしています。
つまり、AIは仕事を一律に奪う存在ではなく、AIを使いこなせるかどうかが、仕事の将来を左右するという見方が広がっています。体力や現場対応が求められる仕事は、短期間で完全に置き換えられる可能性は低いと考えられています。
こうした議論は、日本にとっても他人事ではありません。
ASEANと日中韓の経済調査機関「AMRO」による試算では、日本はAIによって自動化される可能性の高い職種の割合が14.4%と、アジア諸国の中で最も高い結果となりました。
<参考>生成AI 国内動向まとめ(2024年4月)
その背景には、日本では事務職をはじめとするAIに置き換えられやすい職業の比率が高いことがあると指摘されています。
しかし、こうした状況を単なる脅威として捉えるのではなく、AI時代にどのような仕事がなくなり、どのような仕事が生まれるのかを正しく理解することが重要です。
本記事では、AI時代のキャリア構築に必要なスキルや考え方、AI活用のポイントを分かりやすく解説します。
1. AIで仕事は奪われる?なくなる仕事・生まれる仕事の現実【職業別】
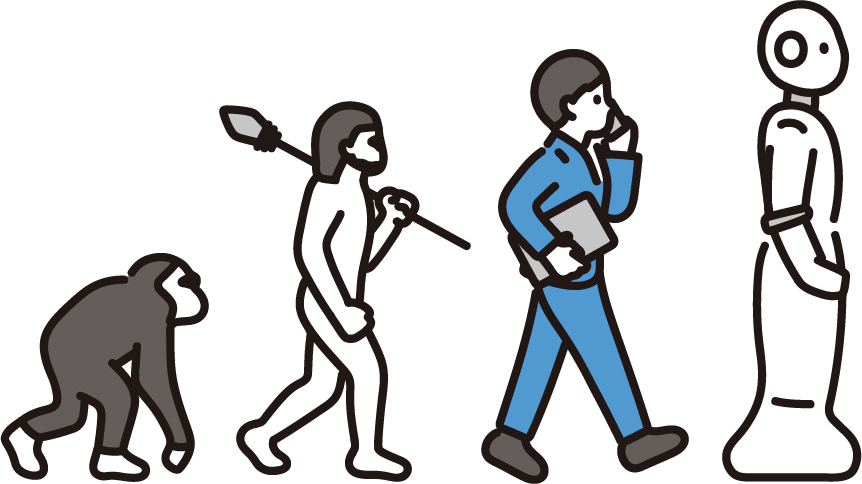
「AIに仕事を奪われる」と聞くと、不安になる方も多いかもしれません。実際に、AIはすでに一部の仕事を自動化し始めており、その影響は広がりつつあります。ただし、すべての仕事がなくなるという意味ではありません。
AIが進化することで、人間にしかできない仕事や、新しい職業も生まれてきています。ここでは、「AIによってなくなる仕事」と「AIによって生まれる仕事」、そして日本の雇用の今について、具体的な事例とデータをもとに詳しく解説します。
日本でAIの影響を受けやすい仕事・職業一覧
AIが得意なのは、同じ作業を繰り返す業務やルールが決まっている処理です。そのため、すでに一部の職種では、AIによる自動化が進んでいます。
| 職業 | 具体例 |
| 一般事務・経理業務 | データ入力や帳簿作成は、AI-OCRやRPAによって効率化が進む |
| コールセンター | チャットボットや音声応答AIが、問い合わせ対応を代替する |
| 翻訳業務 | AI翻訳ツールにより、リアルタイムかつ多言語の翻訳が実現する |
| 会計監査・通関手続き | ルールに基づくチェック作業は、AIによる自動化が可能 |
これらの仕事に共通するのは、定型的な業務やルールに従って処理する作業であることです。とりわけ企業においては、スピード・正確性・コスト削減が重視されるため、AIによる自動化との相性が良いとされています。
野村総合研究所の調査によると、「10〜20年以内に日本の労働人口の49%がAIやロボットによって代替可能になる」と試算されています。
<参考>野村総合研究所
AIによって新しく生まれる仕事とは?需要が高まる業種
AIが台頭しているからといって、人間の仕事が全てなくなるわけではありません。むしろ、AIと協力するための新しい職業や役割が続々と登場しています。
| 職業 | 具体例 |
| プロンプトエンジニア | 生成AIに的確な指示(プロンプト)を与える専門職 |
| データ分析職・AIトレーナー | AIが扱うデータを整理・分析・活用するスペシャリスト |
| AI支援医療技師 | 遠隔医療や診断補助にAIを導入する医療現場での技術者 |
| データ探偵(Data Detective) | AIの出力をもとに、問題解決のヒントを導き出す専門家 |
これらの職業に求められるのは、単に「AIを操作するスキル」ではありません。AIが出した情報をどう判断し、どう活用するかといった人間ならではの判断力や発想力、倫理的な視点が求められます。
つまり今後は、「AIをどう使うかを考え、適切に使いこなせる力」こそが、キャリアを築くうえで大きな強みになるといえるでしょう。
2. AI活用が仕事に求められる理由と、日本の現状(AI導入の遅れ)
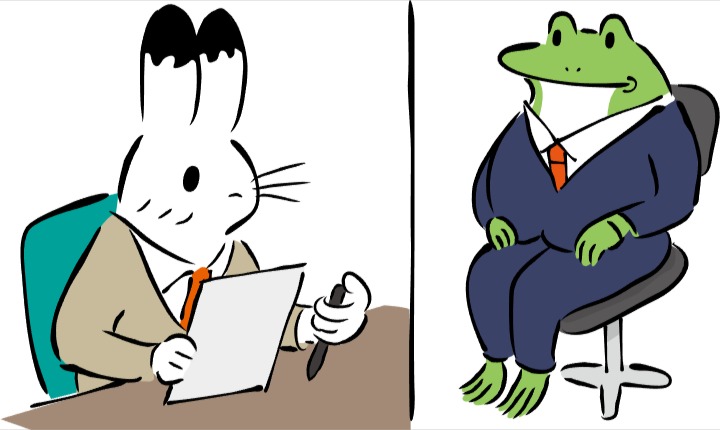
デジタル化が進む中で、企業が人材に求めるスキルにも大きな変化が起きています。なかでも注目されているのが、「AIを使える人材」や「データを扱える人材」です。
一方、日本では依然としてAI活用に対して消極的な傾向が根強く、世界の潮流とギャップが広がりつつあります。ここでは、採用現場の動向と日本の現状、そしてその背景にある課題を整理してみましょう。
仕事で求められるスキルは「AIを使える力」へ
近年の採用市場では、「AIやデータ分析のツールを使えるかどうか」が、書類選考や面接の評価ポイントになりつつあります。
たとえば、次のようなスキルが注目されています。
- AIチャットツールやRPAの活用力
- データ収集・分析・可視化の経験
- 業務フローを自動化・最適化する実践力
PagerDutyの調査によると、グローバル企業幹部の74%が「AIなしでは業務に支障が出る」と回答しています。また、ソフトウェア開発分野では、すでに84%がAIによるコード生成やレビューを導入済みであり、実務にAIスキルが組み込まれていることがわかります。
このように、AIはもはや一部の専門職だけでなく、「現場の誰もが使うツール」として位置づけられつつあり、それを使えるかどうかが採用の大きな判断材料となっています。
日本のAI活用はなぜ遅れているのか?失業リスクへの影響
AIをめぐる世界的な意識と比較すると、日本はその理解度・活用度ともにかなり低い水準にとどまっています。
IpsosのAI意識調査によると、日本で「AIを理解している」と答えた人は41%にとどまり、世界30か国中で最下位となっています。また、「AIによって自分の仕事が良くなる」と回答したのもわずか20%で、こちらもほぼ最下位という結果でした。
このような傾向は、個人だけでなく企業にも共通しています。AIの活用に対して不安や懸念を持つ人が多く、導入や教育に消極的な企業も少なくありません。
<参考>Ipsos AI意識調査
なぜ日本はAI活用が遅れているのか?3つの理由
日本のAI導入が進まない背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。多くの理由としては、「何に使えるのか分からない」「成果が見えにくい」「社内にノウハウがない」といった声が挙げられます。
その背景にある構造的な課題は以下の通りです。
- 教育の遅れ:AIリテラシー教育が普及しておらず、社会人も学生も「使い方がわからない」状態に陥りやすい。
- 企業文化の保守性:年功序列やトップダウンの風土が、現場レベルでの技術導入を妨げている。
- リスク回避志向:「前例がないことを避ける」「失敗を恐れて挑戦しない」という文化が根強い。
このような背景から、日本では「AIを使うべきと分かっていても使えない」状態に陥っているケースが見られます。
<参考>総務省|情報通信白書
3. AI時代に仕事を奪われないために必要なスキル
「AIに仕事を奪われる」とよく言われますが、それはAIの本質を見誤った考え方です。実際には、AIは人間の仕事を代わりに行う“敵”ではなく、人間の生産性を高めるための道具=ツールです。
そして、これからの社会では「どんなツールを、どう使いこなせるか」が個人の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。ここでは、特にビジネスの基盤となる「情報収集力」に焦点を当て、AI時代に身につけておくべきスキルについて考えていきます。
AIは「仕事を奪う存在」ではなく、「人間を支えるツール」
AIは確かに、定型的な業務や反復作業を自動化する力を持っていますが、その本質は“代替”ではなく“補助”です。業務の一部をAIが担うことで、人間はより価値の高い業務(判断、創造、戦略など)に集中できるようになります。
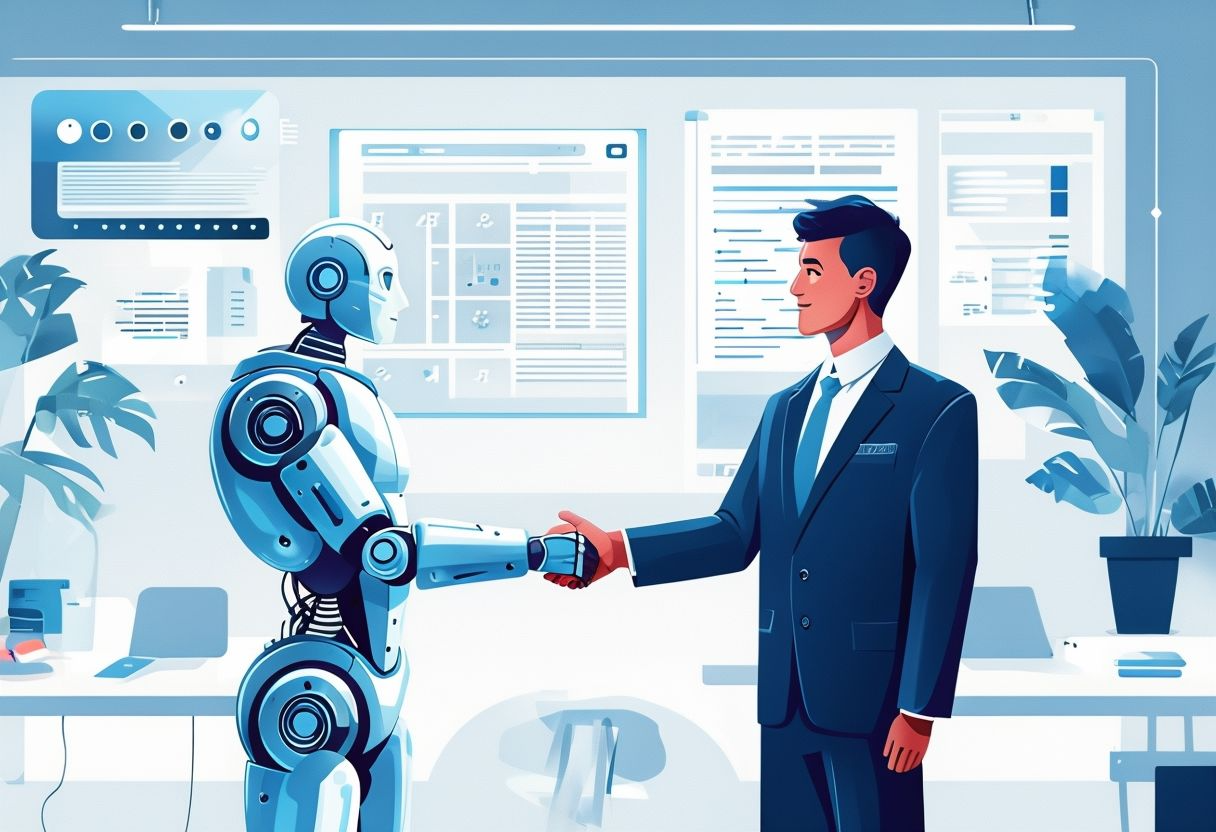
たとえば、以下のような場面で、AIは私たちの働き方を支えています。
- 資料作成や文章の草案作成(生成AI)
- 顧客対応の一次窓口(チャットボット)
- データ分析の自動化(BIツールや予測モデル)
これらのツールは、使う人の目的や知識次第でパフォーマンスが大きく変わるのが特徴です。つまり、AIに何をさせ、どう活かすかを考えられる人こそが、価値ある人材として評価されていくでしょう。
どのツールをどう使えるかが、仕事の差になる
これまでの仕事では、「何を知っているか」や「どんな経験があるか」が評価基準でした。しかし、AI時代ではそれに加えて、「どのようなツールを使って、どうアウトプットできるか」が問われるようになっています。
実際、ビジネスの現場では以下のようなスキルが重視されつつあります。
- 生成AI(ChatGPTなど)を活用したレポート・企画書作成
- RPAツールで定型業務を自動化するスキル
- BIツールでのデータ可視化と報告
- Webスクレイピングツールを使ったデータ収集
これらはすべて、「ツールを使いこなせるかどうか」で成果の質もスピードも大きく変わる領域です。ツールの使い方を知っている人が、今後の職場でリーダーシップを取る可能性はますます高まるでしょう。
まず身につけたいのは情報収集スキル|AI時代の基本
さまざまなツールが登場する中で、最もベースとなるのが情報収集力(データリテラシー)です。なぜなら、AIを使うにも、意思決定をするにも、「正しい情報を集めること」からすべてが始まるからです。
情報収集力が重要な理由
- AIの出力は入力次第:「間違った情報を与えると、間違った答えが返ってくる」
- 意思決定の土台:マーケティング、企画、戦略立案など、すべてデータをもとに判断される
- 競合との差別化:誰も見ていない情報源から有益なデータを引き出せる人は強い
たとえば、Webスクレイピングツールを使えば、特定業界の動向、競合企業の最新情報、価格比較などを自動的に収集できます。こうしたスキルがあるだけで、資料作成のスピードや内容の深さが格段にアップします。
したがって、AI時代における情報収集スキルは、すべての仕事に通じる“土台”ともいえるでしょう。
4. AI時代の仕事に役立つ情報収集方法|Webスクレイピング活用例
情報が価値になるAI時代において、「必要なデータをいかに効率よく集められるか」は、ビジネスや学習、日常業務において極めて重要です。そこで注目されているのが、「ウェブスクレイピング」という手法です。
ここではウェブスクレイピングを活用したデータ収集の基本について解説します。
ウェブスクレイピングとは?
そもそもウェブスクレイピングとは、Web上にある情報(テキスト、数値、画像など)を自動的に抽出・取得する技術のことです。例えば、複数のニュースサイトやECサイト、企業の採用ページなどから、手動でコピー&ペーストをせずとも必要な情報を一括で集めることができます。
本来ウェブスクレイピングは、プログラミング(Pythonなど)を用いて行うのが一般的ですが、ウェブスクレイピングツールを使えばノーコードで操作が可能です。
ウェブスクレイピングツール「Octoparse」とは

ウェブスクレイピングツールには数多くのサービスが存在しています。中でもOctoparseはウェブスクレイピングツールの中でもトップクラスのユーザー数を誇る人気ツールです。
Octoparseの特徴は、単に「情報を集める」だけのツールにとどまらないことです。豊富な機能に加え、各AIツールと組み合わせることで、リサーチ・資料作成・業界分析など、さまざまな業務を効率化できます。
具体的な活用シーン
- 就職活動中に業界データを収集する:企業の採用ページから求人条件をまとめたり、志望業界の動向を数値で把握できる
- 生成AIにレポートを書かせるための参考資料を集める:Web上の記事や統計データをスクレイピングし、AIに要約・構成を任せる際の材料にする
- マーケティング調査や競合分析に活用する:競合企業の価格、サービス内容、口コミなどをまとめて収集し、自社戦略に反映する
- SNSやニュースサイトからトレンド情報を抽出する:リアルタイムの市場感覚を把握するための定期モニタリングが可能
このように、Octoparseを活用すれば、「探すのに時間がかかる」「情報が分散している」といった課題を一気に解決できます。
初心者がOctoparseを活用するメリット
「スクレイピングって難しそう…」という印象を持っている人も少なくありません。しかし、Octoparseは直感的に操作できるUIと、豊富なチュートリアルやテンプレートが用意されており、プログラミング未経験者でも短期間で使いこなせるように設計されています。
主なメリットは次のとおりです。
- GUIベースの直感的な操作だけで対象データを指定できる
- 数百種類ものスクレイピングテンプレートがあり、わずかな操作で開始できる
- クラウドで自動実行も可能なため、収集作業を“自動化”できる
https://www.octoparse.jp/template/google-maps-advanced-scraper
5. よくあるご質問(FAQ)
Q1. AIでなくなる仕事・失業リスクが高い職業にはどんな特徴がありますか?
AIの影響を受けやすいのは、作業内容が決まっていて、毎日ほぼ同じことを繰り返す仕事です。
例えば、データ入力や定型的な事務処理、簡単なレポート作成などが挙げられます。
一方で、人とのコミュニケーションや判断が求められる仕事は、短期間で完全になくなる可能性は高くありません。
職種名よりも、「日々どんな業務をしているか」が判断のポイントになります。
Q2. AI時代に仕事を奪われないために、今からできることはありますか?
AI時代に仕事を奪われないためには、AIを使いこなすスキルを身につけることが重要です。AIを避けるのではなく、業務効率化や情報収集に積極的に活用できる人材は、今後も需要が高まると考えられます。
特に、情報を集めて判断につなげる力や、AIツールを業務に取り入れる経験は、AI時代のキャリア形成において大きな強みとなります。
Q3. 会社にAIが導入されたら、本当に人員削減やリストラにつながるのでしょうか?
AIが導入されたからといって、すぐに人員削減が行われるケースは多くありません。
ただし、これまで人が行っていた事務作業や資料作成などがAIに置き換わり、仕事の内容や役割が少しずつ変わっていくケースは増えています。
将来を考える上では、「AIに仕事を奪われるかどうか」よりも、AIを活用して仕事ができるかどうかが重要になってきます。
まとめ:AI時代のキャリアは、情報を集める力から始まる
AIの進化に不安を感じるのは自然なことです。しかし、「AIに取って代わられる側」ではなく、「AIを使いこなす側」に立つことで、キャリアの選択肢は確実に広がります。
その第一歩として、正確な情報を効率よく集める力=情報収集力を鍛えることが大切です。WebスクレイピングツールのOctoparseを使うことで、より効率的にデータ収集が可能になります。AIを活かせる人材になるためにも、まずは情報を自分の手で集めるところから始めてみてください。
💡関連記事:
【必読書&便利サイト】AI(人工知能)学習の王道ガイド2025年版!初心者から上級者まで12冊!
AIエージェントとは?生成AIとの違い、活用メリットや課題を解説
【2025年最新】生成AIツール最前線!おすすめ31選を紹介
競合サイト・EC・地図・SNS の情報を、Excel・CSV・Google Sheets にそのまま出力。
クリック操作だけで、価格・レビュー・店舗情報など必要な項目を自動抽出。
Google Maps・食べログ・Amazon・メルカリ向けテンプレートで、すぐに取得開始。
大量取得や定期実行でも止まりにくく、競合監視を継続できます。
毎日・毎週のデータ取得をクラウドで自動実行し、更新を見逃しません。
世界 600 万人以上が利用し、主要レビューサイトで高評価を獲得。